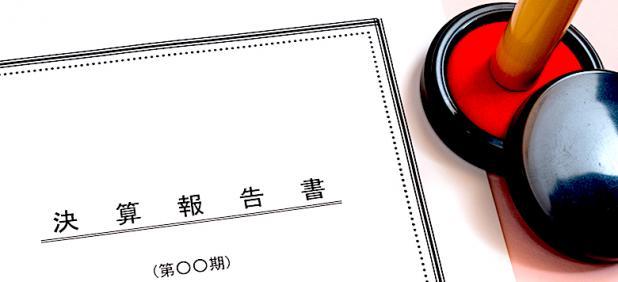土地の等価交換の特例について
「利害関係のない法人同士」で不動産を交換する時、A社の簿価が土地10,000,000円建物1,000,000円B社の簿価が土地10,000,000円建物5,000,000円だった場合、どうしてもB社がA社の土地建物を入手したいため等価交換(差額の金銭授受は無し)をした場合。
1.実際の簿価の差額に対して税額(A社贈与税)は発生しますか?
2.そもそも建物の簿価が4,000,000円差があるんですが交換は出来ますか?
3.また利害関係のある法人同士(社長同士が身内とか)だと変わってきますか?
4.それからそれぞれ土地を交換した後の両社の帳簿にはそれぞれいくらの土地と建物を計上すればよいのでしょうか?
A社は土地10,000,000円 建物5,000,000円
B社は土地10,000,000円 建物1,000,000円
とすればいいのでしょうか?
それとも
A社土地10,000,000円 建物1,000,000円
B社土地10,000,000円 建物1,000,000円
でしょうか?
普通は利害関係ない会社同士だと不動産の価値が違うと必ず差金が発生すると思うので経理は簡単ですが最初に説明してるようにB社がA社の土地建物をどうしても入手したいためにA社が交換によって税額負担ないようにしたいと思ってます。
またその条件で交換してくれるという事です。それとB社の不動産の方が簿価が高いので交換した時に税務署から差額は贈与の対象になると言われる可能性があるのではないかと思ったのでお聞きしました。
長々とすみませんかどうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答
土地・建物を交換する場合はそれぞれ時価(簿価ではありません)により交換したものされますので、その時価が原則として等価であれば、その譲渡益は「固定資産の交換特例」により、課税が繰り延べられます。法人税では「圧縮記帳」という処理をします。
つまり、旧土地・建物を時価で譲渡し、その代金で交換資産を取得したものとされます。
なお、土地同士・建物同士が等価であることが条件です。しかし、仕様の異なる土地同士あるいは建物同士がぴったりと等価になることは稀なので、その差額は金銭で収受することになります。その収受した金銭の額が時価の20%以内であれば「固定資産の交換特例」を適用することがあります。
ところで、時価とは一般的な売買相場をいいますが、どうしてもその不動産を手に入れたい場合は、相場より少し高くても買おうとするはずですので、その場合は、相場より若干高くても上記でいう「時価」と認められます。
ちなみに、「贈与」とは自然人が行う行為なので、法人には「贈与」という行為は発生しません。法人税では「受贈益」「寄付金」という処理で、通常の法人税が課せられます。
土師先生、ご回答ありがとうございます。
法人では贈与と言う言い方はしないのですね。勉強になりました。
ところで今回の件ですが時価は簿価ではないとのことですのでA社B社双方が納得さえしていれば
簿価に差があっても時価を合わせて等価交換できるということでしょうか?
また交換した時、それぞれの帳簿に土地と建物の値段を記載すると思うのですがその時にA社の土地建物の金額(土地1,000万円建物100万円)に合わせて交換することって出来ますか?
ちょっと難しい話しなのですが基本的にB社がA社の不動産を欲しいと思ってるのですがA社は煩わしい作業が嫌なのでそれらをしなくて済むのなら交換に応じると言うことなのでB社としてはA社に負担(税額の発生や複雑な会計処理)をかけたくないと考えています。本来ならば差額が出る取引なので親族でもない法人同士が等価交換するのは変な話なのですがそう言う事情がってちょっといびつなケースになっています。
「簿価」とは買った時の価額ですので、売買(時価交換)する場合には売買する時の相場を勘案するのであって、他人(社)の簿価がいくらであったか考慮することはほとんどといっていいほどありません。
等価交換した場合、例えば、Aの土地の時価(交換価額)が2,000万円、建物の時価(交換価額)が300万円であった場合、
取得したのはBの土地建物ですから、Aの売却収入2,300万円(土地2,000万円、建物300万円)が計上され、同時にBの土地2,000万円と建物300万円が計上されます。
その結果、売却(譲渡)益が1,200万円が計上されますので、この金額の範囲内で、取得したBの帳簿価額を減額します。
Bの土地2,000万円 → 1,000万円(減額 1,000万円)
Bの建物 300万円 → 100万円(減額 200万円)
よって、新たに取得したBの土地建物は、当初所有していたAの土地・建物と同じ金額となります。(「帳簿価額の付替」といいます。)
厳密に言うと、全く同じ価額にはなりませんが、考え方としてはそういうことです。
この1,000万円及び200万円を減額する経理方法を「圧縮記帳」(取得価額を圧縮するという意味)といいます。
土師先生、ありがとうございます。
先生の例え話の時価の場合、A社は1,200万円の圧縮損を計上して新たに取得した土地建物(B社の土地建物)の価格を元の価格(土地1000万建物100万)に合わせる。そうすることによって土地建物を2300万円で売った利益と相殺されてプラマイゼロになると考えてよろしいですか?
A社仕訳
土地建物 2,300万円/土地建物 1,100万円
/売却益 1,200万円
圧縮損 1,200万円/土地建物 1,200万円
一方B社は800万円の圧縮損を計上して元の土地建物の価格(土地1000万建物500万)に合わせるという処理でよろしいのでしょうか?
B社仕訳
土地建物 2,300万円/土地建物 1,500万円
/売却益 800万円
圧縮損 800万円/土地建物 800万円
ところでこの例え話の2300万円と言う時価については何か決まり事と言うか根拠みたいなものってあるんでしょうか?それともA社B社で話し合って決めた時価なので基本的にいくらでも良いという事ですか?
等価交換であるので、元の帳簿価額に合わせるというのが「圧縮記帳」の手法です。
仕訳としては単純に言えば上記通りになります。
第三者間では合意した金額が正当な取引価額と認められるのが原則です。ただし、相場とあまりにもかけ離れていると何かあるのではないかと勘繰られることがありますが、合理的な理由があれば問題は生じないことになります。
土師先生おはようございます。
等価交換であるので、元の帳簿価額に合わせるというのが「圧縮記帳」の手法です。
とありますが本件の場合、A社の帳簿価格に合わせても2社で協議した結果ならOKと言う事でしょうか?それともこの場合B社の帳簿価格に合わせないとダメですか?
私の最終的に聞きたいことが上記でA社の帳簿価格を交換価格にするとA社は税額はもちろん会計上の負担もないわけでB社は損しますがどうしてもA社の土地家屋と交換してほしいと考えてるので別にかまわないと思ってます。
ただ、A社の帳簿価格を交換価格にした場合B社は400万円の損失が出ますがこれを損失として計上しても大丈夫なのかという疑問がります。
実際にはA社とB社の土地建物の金額が違っているので本当にB社が400万円損失が出るのは間違いないのですが税務署側から見た場合納得してもらえるのかがわかりません。
また圧縮記帳が発生しない点も気になっています。
そのあたり、先生はどう思われますか?
やはりこの場合は帳簿価格の高い方で交換価格を設定して安い方は譲渡益を圧縮損計上にしておいた方がいいのでしょうか?
「B社の帳簿価額に合わせる」とか「B社が損する」とかの説明が出てきますが、「売買」や「等価交換」の仕組みが理解されておられるのかが疑問です。
要するに、いくらで売買(交換)するかが問題であって、相手方の帳簿価額がいくらか(相手が手がいくらで買った)ということをいちいち確認しますか、ということです。
物価は時によって変動するものですから、同じものであっても購入時期によって取得価額(帳簿価額)は異なるのは当然です。
通常「売買」は売主から買主への一方通行ですが、「等価交換」は2つの「売買」が双方で同時に起こった事象です。したがって、「等価交換」も売買の一種です。
仮に、双方の土地・建物の時価が2,300万円であれば、
A社は帳簿価額1,100万円の土地・建物を2,300万円で売却するのですから1,200万円の利益、
B社は帳簿価額1,500万円の土地・建物を2,300万円で売却するのですから800万円の利益
となります。
つまり、現在の価額(時価)で売買(交換)するのですから、どちらも損は発生しません。
更に、
A社は交換により、元々B社が所有していた土地・建物を取得するのですが、本来ならばこれを時価の2,300万円を帳簿価額とすべきところを、A社か元々計上していた旧土地・建物の帳簿価額に付け替えるというのが「圧縮記帳」です。
決して、B社が計上していた帳簿価額にするのではありませんし、B社がいくらで買ったかなど全く必要ありません。
したがって、交換価額、上記の例で言うと2,300万円が適正であれば、何の問題もありません。
そのあと、圧縮記帳して譲渡益をチャラにするか、帳簿価額を2,300万円として譲渡益を課税対象にするかは法人の自由です。
「B社の帳簿価額に合わせる」とか「B社が損する」とかの説明が出てきますが、「売買」や「等価交換」の仕組みが理解されておられるのかが疑問です。
要するに、いくらで売買(交換)するかが問題であって、相手方の帳簿価額がいくらか(相手が手がいくらで買った)ということをいちいち確認しますか、ということです。
物価は時によって変動するものですから、同じものであっても購入時期によって取得価額(帳簿価額)は異なるのは当然です。
それは理解しているつもりです。
そうなると時価って言うのはどうやって決めるのでしょうか?
土地だったら路線価とかを参考にして客観的に決める必要があるのでしょうか?
それともA社B社で話しあって売買価格を決めてもいいのですか?と言う話をさせてもらっていたつもりでしたけど伝わってなかったでしょうか。もし、そうでしたらすみません。
例えば等価交換をしなかった場合でそれぞれに売買した時、A社の土地建物をB社が1,100万円で買いますと言った時、A社は土地が無くなって現金が入ってきただけなので譲渡益は出ないので税額も発生しないと思います。
またB社の土地建物をA社が1,100万円で購入した場合B社は400万の固定資産売却損が発生すると思いますがこの時、この売買価格の1,100万円が時価として認められるかどうかを教えてほしいです。
それが認められるのであれば等価交換も同じだと考えますが違うのでしょうか?
上記で説明したように、「時価」とは一般的な売買相場をいいます。
ですので、A社・B社間で話し合って決めても問題ありませんが、一般的な相場(今いくらで売れるかということ)というものがありますので、1,100万円が適正かどうかはわかりません。
結果として1,100万円が適正価額となることはあり得ますが、帳簿価額を時価としていいという理由にはなりません。
なお、時価を路線価・固定資産税評価額から「勘案して」計算することは出来ます。また、いくらで売れるかどうかは、不動産業者に聞けば大体の価額はわかります。
何度も丁寧にありがとうございます。
最後に一つだけよろしいでしょうか?
先生のおっしゃられるこの件の時価の考え方は交換や売買する両者が親族等の所謂身内である時の考え方ではないのでしょうか?それなら相場と言うのもわかるのですが赤の他人(法人同士ですが)同士がお互いの持ち物を売買する時にも世間の相場って必要になってくるものでしょうか?無知で申し訳ないのですがこれだけ教えていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
個人間取引であれば、時価の2分の1以上の価額であれば、問題ないことになっていますが、法人が絡む場合には、時価取引する必要があるという税法の規定があります。なぜなら、法人は利益追求組織だからです。これを「低廉譲渡」といい、法人税で常に問題となるものです。
契約自由の原則があるから戦略として廉価販売もありうるという意見もありますが、法人税の世界(特に税務署)では、時価はいくらかという点を常に念頭に置いている必要があります。
したがって、相場とかけ離れた金額で取引するのであれば、それは法人にとってメリットのある取引である(最終的には損しない)という合理的な要件(理由)が必要となってきます。
土師先生、連絡遅くなってすみません。
色々とありがとうございます。
理解できました。
低廉譲渡一度調べてみます。
本投稿は、2022年07月07日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。