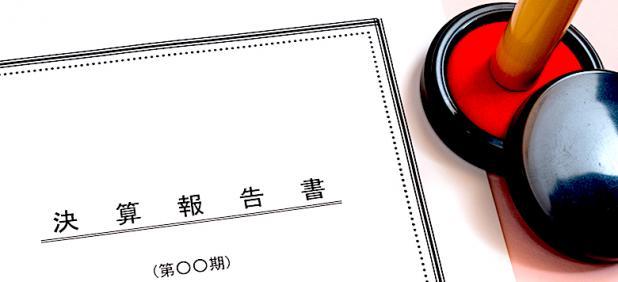準委任契約の常駐案件に関して
企業と請負契約を個人が交わす場合、偽装請負にならない契約としてはどのような形式を取れば良いか教えてください
常駐案件の場合で企業の社員と同じ勤怠管理となり機械設備は企業のものを使用することになる。また、準委任契約として成果物でなく特定業務の遂行としている。
税理士の回答

小川真文
元SEの常駐案件…の経験税理士として参考を述べさせて頂きます。
請負や業務委託などが偽装請負に当たるかどうかは、当事者間の実質的な指揮命令関係の有無によって判断されます。当事者間に実質的な指揮命令関係があれば、偽装請負に当たることになります。(請負や業務委託などは、指揮命令関係のない対等な当事者関係を本質としています)したがって、当事者間に指揮命令関係が認められる場合、それは請負や業務委託などではなく、偽装請負(労働者派遣又は労働者供給)です。
当事者間の指揮命令関係の有無は、契約内容のみならず、実際の業務の態様も踏まえたうえで、実質的・総合的に判断されます。具体的には、以下の要素などが考慮されます。
勤務規則が適用されているかどうか、定時があるかどうか、仕事のやり方や時間配分について、詳細な指示が行われているかどうか、勤務場所が指定されているかどうか等で判断頂くことになります。発注者(派遣先・供給先)が細かい業務指示を行ったり、勤務時間の管理を行ったりするのは偽装請負の典型例と言えます。
ですから、指揮命令関係がないことを契約上明記するが大切です。請負や業務委託などの契約上、指揮命令関係がないことを明らかにしておかなければなりません。単に「指揮命令関係がないことを確認する」などと規定するだけでなく、 勤務規則が適用されないことを明記する、作業時間や仕事のやり方や時間配分、勤務場所などは受注者側の裁量に委ねることを明記するなどが必要と思われます。
偽装請負に該当するかどうかの判断に当たっては、契約内容だけでなく、業務実態も考慮されます。業務実態を把握するための方法としては、現場担当者に対するヒアリングが挙げられます。現場担当者に、職場における状況を自由に話してもらい、偽装請負に当たるような実態が存在しないかをチェックすることも考えてください。
「機械設備は企業のものを使用することになる」のは一般的ですが、「常駐案件の場合で企業の社員と同じ勤怠管理」はかなりリスクがありますし、「成果物でなく特定業務の遂行」が、システムの(開発ではなく)運用でしたら細心の注意が必要です。宜しくお願い致します。
この度は、細やかなご回答とご指導を頂き有り難うございます。
指揮命令関係の件では契約内容に勤務規則が適用されないことを明記する、作業時間や仕事のやり方や時間配分、勤務場所などは受注者側の裁量に委ねることを明記する点を確認いたします。
また、企業社員と同じ勤怠管理の点は供給先の企業の担当者と相談してみたいと思います。
特定業務の遂行については、運用でなく開発・製作に当たりますので、安心いたしました。
本投稿は、2022年11月07日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。