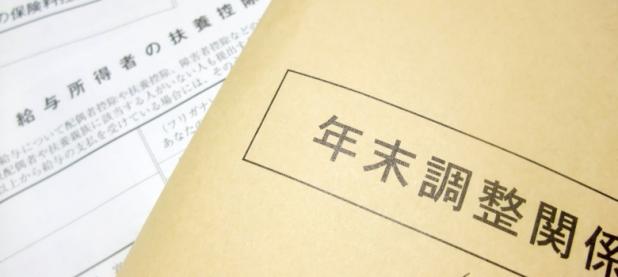法定耐用年数超えの建物をリフォームした場合の、リフォーム部分の耐用年数について
弊社は不動産賃貸業を営んでいる合同会社です。前期中、築47年の木造戸建住宅を購入し、それに300万円かけてリフォームを行った上で賃貸住宅として貸しています。建物部分の取得費用を100万円とした場合、建物の減価償却は、リフォーム後の建物の価値である400万円を4年間で定額償却するということでよろしいでしょうか?それとも、リフォーム前の建物については、100万円を4年間で定額償却、リフォーム部分については、300万円を元の建物とは別に償却すべきでしょうか?その場合、リフォーム部分の耐用年数は何年になるでしょうか?
税理士の回答
中古資産の法定耐用年数は、下記の様に計算します。
「参考」
No.5404 中古資産の耐用年数
[平成30年4月1日現在法令等]
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。
山中先生、ありがとうございました。質問において記載すべきでしたが、ご指摘の国税庁の通達は知っておりましたが、ここに示された指針を具体的状況にどう適用したら良いかが分かりません。弊社の場合、「その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額(300万円)がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)(85平米の戸建なので1100万程度と見積もっています。)の50%に相当する金額(550万円)を超える場合には該当しないので、「法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数」によることがはずです。
また、「その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額(300万円)がその中古資産の取得価額(100万円)の50%に相当する金額(50万円)を超える場合」に当たるので、簡便法による使用可能期間(4年)を適用することはできず、「その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数」によらなければならないということかと理解していますが、正しいでしょうか?仮に正しいとすると、本件のような築47年の中古戸建の場合、「その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数」はどのように考えたらよろしいでしょうか?300万円を投じたとはいえ、築47年の非常に古い木造住宅であり、これがこの先20年、30年と使用できるとは考えていません。しかし、安普請ではなく、大手住宅メーカー施工した有料住宅であり、この先10年くらいは使用できるという感触は持っています。この場合、使用可能期間を10年と見積もっても良いということでしょうか?長くなり恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
法人の減価償却は任意償却ですので、簡便法により見積もられても良いと考えます。
本投稿は、2019年05月03日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。