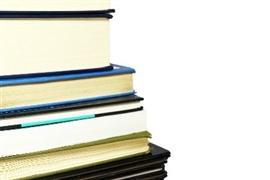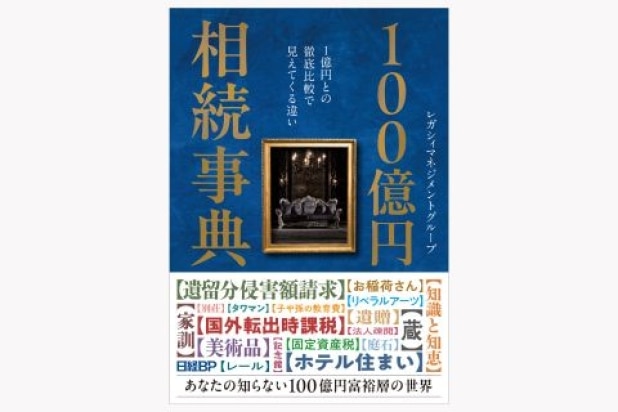改正で封じられた配当や譲渡益の「節税スキーム」 損得の分岐となる所得金額のボーダーラインは?
確定申告

「貯蓄から投資へ」を合言葉に投資を行う人も増えてきたが、実は税制改正により、これまで利用できた節税スキームが使えなくなったのをご存じだろうか?
非課税口座のNISAを除くと、多くの人が利用するのが「源泉徴収ありの特定口座」だが、以下のような3つの特徴がある。
(1)確定申告で「総合課税」を選択すると、所得税は10%(課税所得1000万円超は5%)、住民税は2.8%(同1000万円超は1.4%)の「配当控除」が適用できる
(2)確定申告で「申告不要」を選択すると、上場株式等の譲渡益や配当で得た所得が、事業所得や給与所得などの合計所得金額に含まれない
(3)所得税と住民税で課税方式を別々に選択できる
このうち(3)は、所得税と住民税とで、「申告不要」「確定申告して総合課税」「確定申告して分離課税」を選ぶことができる。
ところが税制改正により、令和5年度の確定申告から、譲渡益や配当で得た所得において、所得税と住民税で課税方式を一致させなければならなくなった。これにより、所得税や住民税にどのような影響があるのか。佐藤 全弘税理士に聞いた。
●改正前は課税所得900万円未満で節税が可能だった
改正前は、前年の譲渡損と本年の譲渡益を相殺するため、または配当控除を受けるために、所得税の確定申告をして還付を受けることができました。
さらに住民税は「申告不要」を選択すれば、その所得は住民税の計算から外れるほか、国民健康保険料などの計算に影響を与えないようにすることも可能でした。
しかし今後は、所得税と住民税とで異なる課税方式を採用できません。そのため、国民健康保険等に加入している自営業者や年金受給者、そして、確定申告をすることによって所得控除等に影響が出てしまう人は、所得税、住民税、国民健康保険料がいくらになるかを考慮し、総合的に課税方式を判断する必要があります。
それでは、配当所得を得ている人が、課税方式の選択で所得税・住民税がどうなるか、3つのケースでシミュレーションしてみましょう。
【条件】
課税所得800万円の人が配当所得を年100万円(源泉徴収後)得ている場合
【課税方式】
・源泉徴収(申告不要)/所得税15%、住民税5%
・分離課税(確定申告をして譲渡損失との損益通算)/所得税15%、住民税5%
・総合課税(確定申告をして配当控除)/所得税0〜40%、住民税7.2%または8.6%(いずれも配当控除適用後の税率)
<ケース1>所得税は総合課税、住民税は申告不要または分離課税
→所得税120.8万円、住民税80.2万円、合計201万円
<ケース2>所得税・住民税ともに申告不要または分離課税
→所得税122.9万円、住民税80.2万円、合計203.1万円
<ケース3>所得税・住民税ともに総合課税
→所得税120.8万円、住民税82.4万円、合計203.2万円
※実際の所得税算出では復興特別所得税を含めて計算
このように、「所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択」する<ケース1>の合計額が一番少額となります。
まず、配当金の所得税については、すでに15%が源泉徴収されています。確定申告で総合課税を選択すると、配当所得を加算した課税所得が900万円未満の場合は、所得税率23%から配当控除10%を差し引くと13%となるため、総合課税で申告したほうが有利となります(総合課税13%<申告不要または分離課税15%)。
そして配当金の住民税は、すでに5%が源泉徴収されているのに対して、一律10%です。確定申告で総合課税を選択すると、住民税10%から配当控除2.8%を差し引き7.2%となるため、分離課税または申告不要のほうが有利となります(総合課税7.2%>申告不要または分離課税5%)。
課税所得900万円未満であれば、所得税では総合課税のほうが税率は低いため、これまでは課税所得900万円未満かどうかが、どの課税方式を選択すれば有利か不利かの判断基準となっていました。
●今後は課税所得695万円未満が有利不利の判断基準に
令和5年分からは、所得税・住民税ともに同じ課税方式で申告しなければなりません。つまり、<ケース2>または<ケース3>のいずれかを選ぶ必要があります。
分離課税または申告不要で20%(所得税15%+住民税5%)なのに対して、総合課税では17.2%(所得税10%+住民税7.2%)の税率となるのが「課税所得695万円未満」ですので、課税方式の判断基準としては「課税所得695万円未満」かどうかが目安となるでしょう。
なおこの場合においても、国民健康保険料等にも影響があるため、こちらも含めて判断する必要があります。
●分離課税で確定申告する場合の注意点は?
上場株式等の譲渡所得等や配当等は、分離課税で確定申告しても申告不要でも税率は変わらないため、所得税・住民税においてもその税額自体に影響はありません。
しかし、確定申告をすることで、所得控除などの判定をする際の合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの適用を受けることができなくなり、世帯全体ではかえって税額が増加する場合がありますので注意が必要です。
また、住民税や国民健康保険料の納付の際などに、確定申告をしないほうが税額の負担が少なくなると気がついても、のちに更正の請求(減額する)または修正申告をすることができません。そのため所得税の確定申告の際には、慎重に検討する必要があります。
【取材協力税理士】
佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士
お客様の立場にたって、わかりやすい税金を目指すとともに付加価値の高いサービスを提供することをモットーに、お客様のニーズに応えられるパートナーを目指して活動している。
事務所名 : 佐藤全弘税理士事務所
事務所URL:https://satouzeirishi.com/