【図解】会社設立に必要な「登記申請書」と「添付書類」の書き方をわかりやすく解説
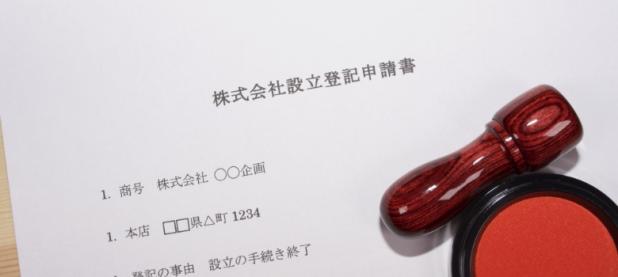
会社を設立して法人格を得るには、法務局に登記申請をしなければなりません。登記申請には、登記申請書のほかにも多くの書類が必要になります。どのような書類が必要になるかは、設立する会社に取締役会があるかどうか、現物出資をしているかなどで異なります。
この記事では、「登記すべき事項」や「登記申請書」、「添付書類」の作成時に注意するべき点をわかりやすく解説いたします。また、各書類の雛形を用意しましたので活用ください。
目次
登記申請の流れ
登記申請は、資本金払込後2週間以内に登記申請に必要な書類を法務局に提出し、登記官からの審査を経て完了します。
この期間を過ぎて登記することも可能ですが、100万円以下の過料に処せされることがありますので注意してください。
提出は、「オンライン申請・郵送・持参」のいずれかの方法で行い、通常であれば申請から1週間〜10日ほどで登記が完了します。
登記完了予定日は、申請書窓口の案内板にて確認できます。また、オンライン申請の場合はオンライン上で、不備の内容や手続きが完了したかどうかを確認できます。
原則として代表取締役が手続きを行うことになりますが、登記の専門家である「司法書士」であれば代行することが可能です。登記は司法書士の独占業務となっているため、その他の士業は代行できないので覚えておきましょう。
登記申請場所
登記申請をする場所は、「登記申請をする会社やその他の法人の本店や支店、もしくは主たる事務所や従たる事務所の所在地を管轄する登記所・法務局・地方法務局・これらの支局や出張所」です。
はじめて会社設立をする場合は、「設立する会社の本店所在地を管轄する法務局」と覚えておけば大丈夫です。詳しくは法務局のHPを参照してください。
登記申請にかかる費用
登記申請するには、登録免許税を納めなければなりません。納める金額は、法人格の種類によって異なります。
| 法人格の種類 | 課税標準金額 | 税率 |
|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金額 | 0.7% (最低15万円) |
| 合同会社 | 資本金額 | 0.7% (最低6万円) |
| 合名会社・合資会社 | 申請件数 | 1件あたり6万円 |
登録免許税の納付方法
登録免許税の納付方法には、「現金納付」と、「印紙納付」があります。
現金納付の場合は、銀行窓口で法務局を管轄する税務署宛に登録免許税を納付します。その領収書を登録免許税納付用台紙(A4サイズの白紙)の真ん中に貼り付けて契印(※1)し、提出します。
印紙納付の場合は、郵便局か法務局内の印紙売り場で収入印紙を購入し、登録免許税納付用台紙の真ん中に貼り付けて提出します。このとき、収入印紙には割印(※2)はしません。
オンライン申請の場合は、「処理状況表示」「アクションメニューの登録免許税付用紙の印刷」をクリックして印刷した用紙を用いて納付することになります。
※1 契印:2枚以上の書類のつなぎ目に、そのつながりが真正である証拠に押す印
※2 割印:2枚以上の独立した文書が関連していることを示すために、各文書にまたがるように押す印
登記申請の注意点
会社の設立日は「登記申請を行った日」となります。
郵送で登記申請を行う場合は、申請書類の到着日が登記申請を行った日となるので、設立日を指定したい場合は注意してください。また、法務局が休みである土日祝日は申請ができませんので設立日とすることができません。
申請に不備があったとき
申請内容に不備がある場合は、原則として申請が「却下」されます。
不備の内容が補正できる内容であれば、電話またはオンライン上で補正の指示があり、訂正して再度提出することになります。ただし、申請人が補正を行わないまたは補正ができなかった場合は、申請が却下されます。
申請が却下されると、申請書が返却されないため、再び申請書を作成することになってしまいます。また、貼り付けた収入印紙も返却されないため、納めた登録免許税については現金で還付を受けることになります。
補正箇所が多くて再提出した方が早い、という場合は申請を「取下げる」ことも可能です。
取下げは、「登記申請書の取下書」を提出することで認められます。取下げの場合は、申請書も添付書類も返却され、再使用証明を法務局から受けると収入印紙の再使用ができます。
そのため、補正の範囲で対応できないほどの不備があった場合は、取下げをして再申請すると良いでしょう。登記が完了するか却下が決定するまでならばいつでも行えます。
※申請書に押印するのは印鑑届書に押印した個人の実印です。
オンライン申請の場合は、申請用総合ソフトに取下書の様式があるので、電子署名を行った上で申請システムに送信します。
登記申請に必要な書類

登記申請には、「登記すべき事項」をデータや紙に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものが必要になります。
手書きで書類を作成する際は、黒インクのボールペンなど消せないものを使用してください。
「登記すべき事項」とは
登記簿に記す内容を法律に沿って記載したもので、会社法および商業登記規則により定められています。
たとえば、「株式会社を発起設立する場合の登記すべき事項」は以下のとおりです。基本的には定款に記載したものと同様の内容になります。
- 商号
- 本店住所(※)
- 公告の方法
- 目的
- 発行可能株式総数
- 発行済株式の総数
- 資本金額
- 株式の譲渡制限に関する規定
- 役員に関する事項
- 取締役会・監査役の設置
- 「発行可能株式総数」「発行済株式総数」とは?株の金額や発行数の決め方は?
- 会社の機関設計はどのように決める?基本的なパターンやポイントを解説
- 【図解】定款の作成ルール〜書き方や割印、製本、訂正方法までわかりやすく解説
※本店住所
定款に記載する場合は、最小行政区(東京都は区、その他は市町村)までで良いですが、登記すべき事項に記載する場合は、詳しい住所まで記載しなければいけません。
たとえば、定款には「東京都港区」まで、登記には「東京都港区六本木○丁目○番○号」と記載します。ビル名や部屋番号は任意となっております。
登記すべき事項は「オンライン申請」「磁気ディスク」「申請書に直接記載」のいずれかの方法で法務局に提出する必要があります。以前は「OCR用申請用紙」で手続きができましたが、現在は配布が終了しています。
オンライン申請で提出する場合
「登記すべき事項」と「登記申請書」を専用ソフトで一括して作成します。
法務省のHPから専用ソフトをダウンロードし、申請書の作成画面で登記すべき事項まで入力し、データを送信します。その後、登記申請書を印刷し、添付書類とともに製本して郵送・持参します。
また、登記すべき事項のみをオンライン申請することも可能です。その場合は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。
磁気ディスクで提出する場合
登記すべき事項を電磁的記録媒体(※)に書き込み、提出します。以前はFDに書き込んで提出することができましたが、現在は使用できなくなっています。
※CD(DVD)-ROM(120mm、JIS×0606形式)、CD(DVD)-R(120mm、JIS×0606形式)
また、作成時には以下の点に注意してください。
- 文字コードはシフトJIS、すべて全角文字で作成する
- TABを使用せず、空白部分は全角スペースを使用する
- フォルダを作らず、テキスト形式で記録する(ファイル名は◯◯◯.txt)
- 磁気ディスク本体に会社の商号を記載したシールやラベルを貼る
申請書に直接記載する場合
登記すべき事項を、申請書に直接記載または、任意の用紙(別紙)に記載し申請書にとじ合わせて契印をして提出します。
「登記申請書」の作成例【図解】
では、実際にどのように登記申請書を作成するのか、記入例をみながら解説いたします。

A:受付番号票貼付欄
1枚目の最上部には、受付番号票の貼り付け欄として、スペースを空けておきます。
B:商号
(株)などと省略せず、正式名称で記載します。
C:本店の住所
本店の住所はハイフンで省略せず、号までしっかりと記載します。
D:登記の事由
設立の手続きが終了した年月日は、出資の履行調査終了日になるため、資本金の払込証明書に記載された年月日になります。登記申請は、この日から2週間以内に行う必要があります。
E:登記すべき事項
直接記載する場合や磁気ディスクで提出する場合は、この部分を「別紙のとおり」や「別添えCD−Rのとおり」とします。オンライン申請の場合は、そのまま続けて登記すべき事項の入力画面になります。
F:課税標準金額
会社設立の場合は資本金額になります。1000円未満は切り捨てます。
G:登録免許税
資本金額の0.7%を記載します(15万円が下限)。100円未満の端数金額は切り捨てます。
H:添付書類
添付書類の種類とそれぞれが何通あるかを記載します。取締役会設置や現物出資の有無によって、必要な添付書類が異なります。
I:日付
法務局の窓口に申請書を提出する日を記載します。
J:署名
会社の本店住所・商号・代表取締役の住所・氏名・補正の場合の連絡先の電話番号を順に記載します。
k:申請先法務局
申請先の法務局の宛先御中と記載します。
L:印鑑
会社の実印を用います。また、捨印も押印します。
M:契印
2枚以上にわたる場合は、会社の実印にて契印をします。手書きで作成する際に、訂正箇所があったら訂正印を押して「◯字削除・◯字加筆」と記載します。
取締役会を設置する株式会社の設立登記申請書」のダウンロードはこちら(Word)
取締役会を設置しない株式会社の設立登記申請書」のダウンロードはこちら(Word)
登記申請に必要な添付書類一覧
添付書類は、会社に取締役会を設置するかどうか、資本金の拠出方法で異なります。
取締役会を「設置する」株式会社
| 書類 | 署名捺印者 | 印鑑 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税納付用台紙 | ー | ー | 領収書や収入印紙を貼り付ける |
| 定款 | 発起人全員 | 個人の実印 | 電子定款の場合は電磁的記録媒体、紙の定款の場合は定款の原本1部 |
| 設立時発行株式および資本金・資本準備金に関する発起人の同意書 | 発起人 | 個人の実印 | 定款に記載があれば不要 |
| 設立時取締役、設立時監査役選任および本店所在場所決議書 | 発起人 | 個人の実印 | 定款に本所在地の番地まで定めていれば不要 |
| 設立時代表取締役選定決議書 | 取締役 | 個人の実印 | 設立時取締役の過半数の一致で選定する |
| 設立時代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役 | 個人の実印 | 設立時代表取締役選定決議書と兼ねている場合、または取締役が1人の場合は不要 |
| 取締役・監査役の就任承諾書 | 取締役・監査役 | 個人の実印 | 就任には承諾が必要 定款に記載があれば不要 |
| 代表取締役の印鑑証明 | ー | ー | 3か月以内に発行したもの |
| 取締役・監査役の本人確認証明書 | ー | ー | 印鑑証明書の添付でも可 定款に記載があれば不要 |
| 資本金の払込証明書 | 代表取締役 | 会社の実印 | 資本金が払い込まれた発起人代表者の通帳のコピーを綴じる |
| 印鑑届書 | 代表取締役 | 会社の実印 個人の実印 | 設立登記の申請書と一緒に提出する |
取締役会を「設置しない」株式会社
| 書類 | 署名捺印者 | 印鑑 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 登録免許税納付用台紙 | ー | ー | 領収書や収入印紙を貼り付ける |
| 定款 | 発起人 | 個人の実印 | 電子定款の場合は電磁的記録媒体、紙の定款の場合は定款の謄本1部を提出する |
| 設立時発行株式および資本金・資本準備金に関する発起人の同意書 | 発起人 | 個人の実印 | 定款に記載があれば不要 |
| 設立時取締役、設立時監査役選任および本店所在場所決議書 | 発起人 | 個人の実印 | 定款に本所在地の番地まで定めていれば不要 |
| 設立時代表取締役選定決議書 | 取締役 | 個人の実印 | 設立時取締役の過半数の一致で選定する |
| 設立時代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役 | 個人の実印 | 設立時代表取締役選定決議書を兼ねている場合は不要 |
| 取締役の就任承諾書 | 取締役 | 個人の実印 | 取締役に就任するには承諾が必要 |
| 取締役全員の印鑑証明書 | ー | ー | 3か月以内に取得したもの |
| 取締役全員の住民票 | ー | ー | 3か月以内に取得したもの ※平成27年2月末から必要になりました |
| 資本金の払込証明書 | 代表取締役 | 会社の実印 | 資本金が払い込まれた発起人代表者の通帳のコピーを綴じる |
| 印鑑届書 | 代表取締役 | 会社の実印 個人の実印 | 設立登記の申請書と一緒に提出する |
現物出資があるとき
資本金に現物出資がある場合は、上記に加えて以下の3つの書類が必要になります。
| 書類 | 署名捺印者 | 印鑑 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 調査報告書 | 取締役・監査役 | 個人の実印 (個人印でも可能) | 現物出資などの変態設立事項がある場合に必要 |
| 財産引継書 | 発起人 | 個人の実印 (個人印でも可能) | 現物出資など、変態設立事項がある場合に必要 |
| 資本金額の計上に関する証明書 | 代表取締役 | 会社の実印 | 現物出資などの変態設立事項がある場合に必要 |
現物出資額が500万円を超えている場合は、検査役の選任申立てをするか弁護士や税理士などが作成した証明書が必要になります。
添付書類の作成例【図解】
添付書類についても、実際にどのように作成するのか、記入例をみながら解説いたします。
設立時発行株式および資本金・資本準備金に関する発起人の同意書
設立時の発行株式・資本金・資本準備金を定める書類です。
定款に定めるのが一般的で、その場合は登記申請書に「発起人の同意書は、定款の記載を援用する。」と記載すれば、この書類の作成は不要になります。
定款に定めていない場合は、発起人の個人の実印を用いて、以下のように書類を作成します。

設立時取締役、設立時監査役選任および本店所在場所決議書
設立時の取締役・監査役・本店所在地を定める書類です。
発起人の過半数の一致で決定されます。定款で役員を定めている場合は、この書類は不要になります。本店所在地も、番地まで定款で定めていれば不要です。
定款で定めていない場合は、発起人の個人の実印を用いて、以下のように書類を作成します。複数ページになる場合は、各ページに発起人のうち1名の契印をしてください。

設立時代表取締役選定決議書
設立時の代表取締役を定める書類です。
代表取締役は、設立時取締役の過半数の一致で決定されます。取締役が1人の場合や取締役会が非設置の場合は、定款で定めていれば本書類は不要です。
定款で定めていない場合や取締役会を設置している場合は、以下のように書類を作成します。印鑑は個人の実印を使います。

設立時代表取締役の就任承諾書
代表取締役になる人は、「代表取締役の就任承諾書」と「取締役の就任承諾書」の2つを用意します。
取締役が1名の場合は、代表取締役の就任承諾書は不要です。また、設立時代表取締役選定決議書で就任を承諾した旨を記載し、個人の実印を押した場合も不要になります。
上記に該当しない場合は、個人の実印を使い以下のように書類を作成します。

取締役・監査役の就任承諾書
設立時には、取締役全員の就任承諾書が必要です。監査役も同様に作成します。
取締役会設置会社は、個人の実印の押印と本人確認証明書(免許書のコピーなど)の添付が必要になります。
取締役会を設置しない会社は、個人の実印の押印と印鑑証明書が必要です。以下のように書類を作成します。

資本金の払込証明書
資本金を振り込む時点では会社名義の銀行口座はないので、発起人個人の銀行口座に資本金を振り込むことになります。なお、新しく口座を開く必要はありません。
振り込みの証明のために通帳のコピーが必要になるので、通帳がある銀行口座が望ましいですが、通帳を発行しないネットバンクを利用することも可能です。
コピーするのは、「銀行通帳の表紙・支店名や口座番号などが記載されている表紙裏・資本金の入金が記帳されたページ」の3箇所です。
ネットバンクの場合は、「振込先金融機関名・口座名義人名・支店名・口座番号・振込日・振込金額」が記載された画面をプリントアウトします。
払込証明書は会社の実印を用いて以下のように作成します。

払込証明書を作成した後は、払込証明書と通帳のコピーを綴じます。
払込証明書の綴じ方は以下のとおりです。

印鑑届書
設立時の登記申請と合わせて、会社の印鑑の実印登録をしなければなりません。登録した印鑑を登記申請書やその他添付書類に使用します。
申請先は会社の本店所在地を管轄する登記所になります。代表取締役の個人の印鑑証明書が必要になりますが、登記申請書に添付しているため、別途添付の必要はありません。
印鑑届書は法務局の窓口、または法務局のHPからダウンロードすることができます。
オンライン申請の場合は、別途印鑑届出書の郵送が必要です。申請番号または受付番号を印鑑届出書の余白に記入するのを忘れないようにしましょう。
調査報告書
現物出資がある場合は、調査報告書を作成します。
調査報告書は、現物出資された財産の価額が相当であること、財産引継書に記載された財産が実際に出資されたことを報告する書類です。
調査報告書は、定款の認証日と財産引継書の日付以後に作成し、設立時取締役全員の署名押印が必要になります。会社に監査役を設置している場合は、設立時監査役全員の署名押印も必要です。
以下のように作成します。

財産引継書
財産引継書は何が出資されたかがわかるように記載します。たとえば、ノートパソコンを出資する場合は、「メーカー名・商品名・型式・製造年・製造番号・価格」などを記載します。
定款の認証日以後に作成し、現物出資を複数の人が行う場合は、現物出資者ごとに以下のように作成します。

資本金額の計上に関する証明書
資本金額の計上に関する証明書は、資本金額が会社法および会社計算規則に従って計上されたことを証明する書類です。現物出資がある場合は、以下のように作成します。

登記申請書一式の製本方法【図解】
登記申請書類の作成が終わったら、「登記申請書・登録免許税納付用台紙・定款・同意書・決議書・就任承諾書・資本金の払込証明書・印鑑届出書」の順番に並べて、ホチキスで綴じます。
登記申請書の綴じ方は以下のとおりです。

登記申請後にやること
登記が完了したら、税務署や年金事務所での手続きを行います。その際に登記事項証明書や印鑑証明書が必要になるので、法務局またはオンライン上で取得しましょう。
また、役員報酬を決めたり法人口座を開設したり、登記完了後にもやらなければならないことはたくさんあります。
税務関係の手続きであれば税理士に、社会保険関係の手続きであれば社労士に依頼できますので、業務のアウトソーシングも検討してみると良いでしょう。
- 【保存版】会社設立の流れ - 手続きの手順や必要書類、費用を詳しく解説
- 会社設立後の役員報酬はどうやって決める?【議事録のテンプレ付き】
- 法人の青色申告はどうする?会社設立後に行う「青色申告の承認申請書」の手続きまとめ
おわりに
書類の不備として一番多いのは、印鑑にまつわることです。
押す印鑑の種類だけでなく、印影が欠けたりすることの無いように注意してください。修正や再申請の必要が無いように、出来れば他人の目も借りながら作成するのがおすすめです。
司法書士の資格を持っているまたは、司法書士と提携している税理士であれば、その後の顧問税理士も含めて会社設立の代行を依頼することができます。
もっと記事を読みたい方はこちら
無料会員登録でメルマガをお届け!
